
速報です
運用益12兆円超と過去最高

2020年8月7日に2020年度第1四半期(4-6月期)運用益は過去最高になりました。
収益率:プラス8.30%

運用状況について
市場運用開始以来、2008年のリーマンショックの時期を含めても、平均収益率は年率+2.97%、累積収益額は+70.0兆円となっています。


ヨシオ君 クイズです
GPIFは何の略語でしょうか?
むずかしいな


ヒント 経済用語です
わかった!
GPIFで「実費 いまだに 踏み倒し」


・・・
前回のブログ ↓
7月3日に公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(通称GPIF)から2020年1~3月期の年金積立金の運用実績の発表がありましたが、
15年度以来4年ぶりの赤字でリーマン以来だと話題になっています。
以前私のブログでもGPIFを取り上げましたが、運用成績は良いので年金が貰えなくなることはないと書いていました。しかし今年はコロナの影響もあり、年金がどうなってしまうのか不安を煽った記事も見かけましたので、詳しく調べて見ました。
GPIFとは皆さんの年金を運用している機関です。

結論から言いますと、問題はありませんでした。
むしろ私のお手本となる運用方法でした。
ではGPIFの運用実績はどれくらいだと思いますか。
2018年度の収益率はプラス1.52%
2001年~2019年9月末までの収益率はプラス3.03%でした。

しかし先日発表された2019年度の運用成績はマイナス5.2%となっていました。

ただ通期の運用益を見てみるとプラスになっており、2001年度からの実質的な運用利回りは2.39%になっています。


どうですか
皆さんの中には効率よく運用し10%以上の利益率を上げている方もいらっしゃると思います。
もちろん高いほうがいいのですが、その分リスクも高くなるということを考えれば、一概に高いからいいとは言えないです。
年金制度とは
今私達が納めている保険料は、今の高齢者世代に年金を給付する「賦課方式」を採用しており、今後人口減少に伴い、年金を納める人が少なくなった時に備え、年金保険料のうち支払いに充てられなかったものを年金積立金として積み立てています。


積立金は不足分を補うものです。
それは100年間の年金の財政計画の中で使われる予定になっており、
そのため概ね50年程度は積立金を取り崩す必要は生じません。さらに、年金給付に必要な積立金は十分に保有しており、積立金の運用に伴う短期的な市場変動は年金給付に影響を与えません。つまり、ある特定年度に評価益又は評価損が発生したとしても、それが翌年度の年金給付額に反映されることないと言えます。
GPIFの業務運営に関する目標として、運用利回り1.7%を最低限のリスクで確保することが要請されています。
中期計画において分散投資を基本として長期的な観点からの資産構成割合(基本ポートフォリオ)を定めており、資産、地域、時間等を分散して投資することを基本としています。これに基づき年金積立金の管理・運用を行っていくと定められているのです。
ということは、現在までの運用利回りは2.39%にもなっており長期的な運用目標を上回っています。
GPIFのポートフォリオを見ると
- 国内債券:35%
- 国内株式:25%
- 外国債券:15%
- 外国株式:25%

投資の基本とは
分散投資と中長期投資を行い、少しでもリスクを回避することです。
1:分散投資
資産・銘柄の分散投資

異なる値動きをする資産や銘柄を組み合わせて投資を行うのが「資産・銘柄の分散」の手法です。
図のように、複数の資産を組み合わせることで特定の資産や銘柄が値下がりした場合には、他の資産や銘柄の値上がりでカバーする、といったように、保有している資産・銘柄の間で生じる価格変動のリスク等を軽減することができます。
地域の分散

投資対象を日本だけではなく、様々な国や円以外の通貨を組み合わせて行う「地域の分散」の手法です。
例えばある地域の経済状況の変化等によって保有している特定の資産・銘柄が値下がりした場合には、他の資産や銘柄の値上がりでカバーする、といったように、保有している資産・銘柄の間で生じる価格変動のリスク等を軽減することができます。
時間の分散

一度に多額の投資を行うのではなく、少額・定期定額で投資を行うことで、時期による値動きに応じて、価格が高い時期には少なく、価格が低い時期には多く投資を行うのが「時間(時期)の分散」(ドル・コスト平均法)の手法です。
長い目で見ると、一回あたりの投資価格は平準化されていきますので、短期的な急な値下がりなどが生じても、それによって生じる損失の程度を軽減することが可能になります。
2:中長期投資
中長期的に行うことで、複利効果が得られます。
投資期間が長いと複利効果も大きくなっていく傾向があります。
複利効果とは、下図のように、当初の投資元本に加えて、投資で得られた運用益(インカムゲイン)も 元本に加えて再投資され、長期運用することで、乗数的に資産が増えていくことです。

このように
資産形成を行う時、分散投資と中長期投資はリスクを減らす方法として効果があります。
基本ポートフォリオの見直し
GPIFは
2020年4月から5年間の運用基準となる資産構成割合(基本ポートフォリオ)を含む中期計画を公表しました。国内債券の利回りが低迷していることを受け、国内債券の比率を下げ、外国債券を引き上げました。
これにより国内債券、外国債券、国内株式、外国株式の4資産に各25%の均等配分としました。


見直しも必要ね
まとめ
今回の赤字はコロナの影響で一時的に株価下落・為替の変動がありましたが、その後は回復しています。
マスコミは、ある部分を切り取って運用が悪い・赤字だと不安を煽っていますが、年金運用は長期投資ですので、短期間で見るのではなく、トータルの成績を見ていくことが大切です。
私達が普段行っているiDeCo・ NISA・積立NISAもまさにこの手法になります。
またこれから、資産運用、資産形成をやってみたい方もGPIFの運用方法を参考にしてみてください

それにしても運用しているお金が150兆円ってものすごいわね
多分こういう仕事してるとゼロの多さに慣れちゃって150兆円が150万円位の感覚になるんだよ


いやいや国民の年金預かってるんでしょ
私だったらプレッシャーでおなかが痛くなっちゃう
それは腸炎だな
150兆円だけに


座布団一枚



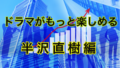

コメント